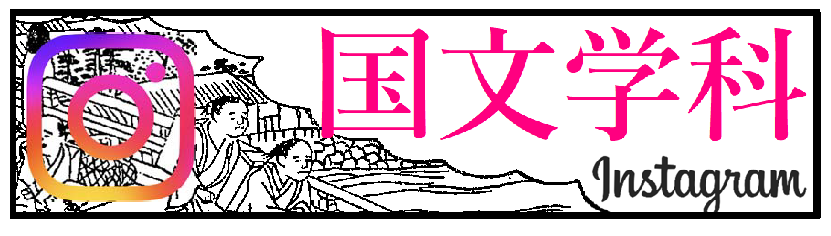140年以上の国文学研究の伝統を持つ国文学科では、先人の心の豊かさを学びとってほしいという思いから、古典の訓詁注釈を学問の基盤としています。また、国文学・国語学に加え、漢文学や書道、図書館学など幅広い分野の専任教員を置き、国文学だけでなく関連科目も充実しています。フィールドワークや文学散歩で名作の舞台となった場所を訪れるなど学外活動も積極的に行い、風土に根ざした作品理解につなげているほか、少人数制の演習・講義によるアットホームな雰囲気の中できめ細やかな指導が受けられるのも本学科の特徴です。美しく、的確な表現力を身に付けた卒業生は社会に出てからも信頼が厚く、幅広い分野で活躍しています。
学科概要国文学科
古典に学ぶ
美しい言葉の世界
学科概要
国文学科で学ぶこと
上代から近世までの古典文学と近現代の文学作品を解読する「国文学」と、日本語の構造や表現などを学ぶ「国語学」の二つを中心に、漢文学・書道・図書館学まで、様々な領域について学びます。各分野にそれぞれ少数精鋭のゼミを開講し、正確に文献を解釈する読解力と、美しく的確な表現力を培います。
幅広い分野に応用できる力
国文学・国語学を通して、自立した社会人に不可欠な「豊かな感受性」「柔軟な思考力」「的確な表現力」を身に付けます。
読解力と表現力を学ぶ少人数ゼミ
それぞれの専門分野にはそれぞれ少数精鋭のゼミが置かれ、正確に文献を解釈する読解力と、美しく的確な表現力を培います。
様々な専門分野を通して国文学を学ぶ
上代から近現代に及ぶ国文学と、国語学・漢文学・書道・図書館学の各分野に専任教員を配しています。
自由に組み合わせられる4コース
「国語学・国文学」「国語教育コース(中高教員)」「書道・漢文学コース」「図書館司書コース」の4コースを設置しています。学生の興味に合わせ、自由に組み合わせて履修することが可能です。
教員一覧(国文学科)
ゼミナール(演習)
上代文学ゼミ

大島 信生 教授
基本テーマ
日本最古の歌集、万葉集の研究方法を修得し、作品を正しく理解することが目標。
3年次のゼミでは、訓詁注釈に根ざした万葉集の研究方法を修得します。万葉集は漢字ばかりで書かれており、原本は存在しません。『校本万葉集』や注釈書を丹念に調べて、本文と訓を定めるところから研究は始まります。その本文や訓に異同のある語句や解釈の分かれるところが問題点となります。その問題点について考察を深め、自分自身の歌の解釈を示せるようにします。4年次のゼミでは、3年次に決めた卒業論文のテーマについて研究を進め、卒業論文の完成を目指します。2年間のゼミで、お互いに切磋琢磨しながら学問の醍醐味を味わってもらえたらと思います。
中世ゼミ

木村 尚志 准教授
基本テーマ
中世を中心とする和歌文学の表現・享受・影響圏について考え、論文のテーマを見つける。
私の専門とする時代は中世で、鎌倉時代の和歌を中心に研究しています。中世は和歌文学の最盛期であり、和歌という文学を通して人間の心を深く見つめる、そのための規範となる古典が定められました。それらの古典については注釈書や歌論書が書かれ、その研究の土台の上に、軍記、芸能、物語、日記、紀行などの豊穣な文学が生まれたのです。中世の豊かな文学や文化の開花の種は和歌である、という実感を得てほしく、私は授業内での能の実演を通して和歌の大切さを伝えています。そこで持った興味を大切に、卒業論文まで育てる応援をします。
近世文学ゼミ

田中 康二 教授
基本テーマ
江戸時代の文学作品をくずし字で読み、正確に解釈し、作品の魅力を語る力を身に付ける。
3年生のゼミでは、春学期にくずし字の読解力と作品の解釈力を養い、秋学期には各自の関心に応じて文学作品を選定し、作品解析のアプローチを身に付けます。4年生のゼミでは、春学期に研究の対象や方法などを絞り込み、綿密な調査計画と執筆計画を立て、自信の持てる卒業論文を完成させます。
近代文学ゼミ

平石 岳 助教
基本テーマ
日本近代文学作品の時代性と普遍性の両方を、様々な資料から検討し理解する。
現代のわたしたちが感じた日本近代文学作品の印象と、作品発表当時の読者たちによる読後感は、大きく異なることもあるし、非常に似ていることもあります。作品には、当時の読者たちだけが気付くような仕掛けや話題があり、それを当時の資料を探ることで追体験していきます。また、ゼミのなかでも作品に対して様々な読み方、感想を持ちます。ひとつの作品に対して、読み手の数だけ感想や解釈が生まれる現場として、ゼミを楽しんでください。
国語学ゼミ

齋藤 平 教授
基本テーマ
日本語を言葉のダイナミックな流れの中で分析的に捉えて解明する。
日本語を分析するといっても、様々な角度からの考察があります。このゼミで目指しているのは、一つの言葉について徹底的にその性格を明らかにしようとすることです。理由を表す「だ=から」は近世までは江戸のことばでした。京や大坂では「や=さかい」が使われていました。しかし、現代では関西でも「や=から」が多く使われ、「や=さかい」はその勢力が衰えました。東海地方では伝統的に「だ=もんで」が優勢で、三重では「や=もんで」になっています。ことばはさまざまな地域からの影響を受け、変容していきます。その背景にあるものを含め、言語科学的な手法でことばの性格を明らかにしていくのです。
書道ゼミ

上小倉 一志 教授
基本テーマ
中国書道史における書体・書風の変遷を石刻資料や歴代能書家の書を中心として学習する。
我々が使用している漢字は、甲骨文・金文に始まり小篆・隷書・草書・行書・楷書とその姿を変えてきました。これら書体の変遷とそこで生まれた書の名品に見られる書風の違いを金文・石刻資料や現存する肉筆資料などを基に学習します。さらに、歴代能書家の書風に大きな影響を与えたであろう時代的背景や地域風土、そして個々の人物像・人間関係などにも触れていくことで、作者がどのような理念を持って書作したのかを探求し、書に対する時代的な考え方の違いやそれによって生み出された独特の表現法を理解していき、その技法を自らの作品制作にも生かしていくことができることを目的としています。
漢文学ゼミ
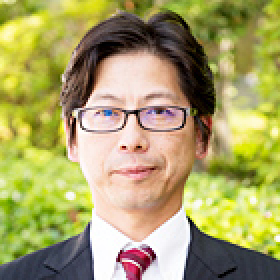
松下 道信 教授
基本テーマ
漢文の読解力を養いつつ、道教を中心に中国の文化や思想に迫る。
漢文学ゼミでは、『列仙全伝』というテキストを読んでいます。これは太古の仙人から、後世、活躍した著名な道士たちまで500人以上もの伝記を絵入りでまとめたもの。明末に中国で出版されるや、本書はすぐさま日本に伝わり、江戸時代にはよく読まれたようです。漢文学ゼミではこの『列仙全伝』を使い、訓点をたどりつつ、そこに書かれた文章を分かりやすく読み進めていきます。その際、書かれている内容を正確に理解するのは当然ですが、その文章の背景まで迫っていくと、そこには思いがけない発見が待っていることもしばしば。時に深遠で、また時に不思議な道教の世界を冒険しつつ、日本に大きな影響を与えた漢文学について学んでいきます。
図書館学・現代文学ゼミ

岡野 裕行 准教授
基本テーマ
読書やメディアの観点から、文学と図書館にまたがる領域について考える。
文学作品が読者にどのように受容されてきたのかについて考えるには、私たちの読書のあり方やメディアの発達の歴史を問い直していく必要があります。どういった場所で読者が本を読んできたのかという読書空間の問題、どういった媒体によって文学作品に触れることができるようになったのかという出版流通の発達や印刷技術の変遷の問題、誰が書物の生産・移動・収集・保存に関わってきたのかという文学を提供する側の人たちの問題など、文学に関する出来事を読書やメディアなどの書物文化の観点から捉え直していきます。また、読書空間の一つには図書館も含まれることから、司書課程の講義内容とも相互に理解が及ぶような内容を意識します。
学科Topics
教室で学ぶだけではありません。多彩な学びを通して成長します。
Topic1フィールドワーク
ゼミごとに、それぞれの研究内容に合わせてフィールドワークを行います。

上代文学ゼミ
ゼミ旅行では、万葉集や古事記などの上代文学作品の故地をその年の研究テーマに応じて訪ねています。これまで九州・山陰・四国・奈良などに行きました。作品の舞台の土地に実際に行くことで作品の理解を深めることができます。

中世文学ゼミ
中世文学ゼミではゼミ生自らが主体的にコースを決めます。「古典文学の舞台を実際に歩いて見て食べて学ぶ」という趣旨で、古典文学の中心である近畿や、中世に重要性を増す関東等が候補地圏内に入ります。令和6年度は、比叡山に登り、琵琶湖を望みました。

近世文学ゼミ
ゼミ旅行では、近世期に書かれた文学作品にゆかりのある土地に行って、その土地の空気を吸い、その土地の風景を楽しみ、その土地のものを食します。令和6年度は「おくのほそ道」を逆行すると題して、平泉・松島・日光・深川を訪れました。

近代文学ゼミ
フィールドワークでは、ゼミで取り扱った近代文学作品の舞台を訪れたり、近代日本において文学と密接な関係にあった演劇・劇場文化を体験します。訪問地は、毎年ゼミ生たちの意見を取り入れながら、みんなで決めていきます。

国語学ゼミ
方言は身近で興味のある言葉ですが、その本格的な研究方法を学ぶ機会は余りありません。このゼミでは、普段接することの余りない言語圏で調査をし、記録や解釈など、総合的にその方法を学びます。

漢文学ゼミ・書道ゼミ
中国の歴史や文化に実際に触れるため、書道ゼミと漢文ゼミのフィールドワークの行き先は、もちろん本場、中国。毎年、書道ゆかりの重要な石碑を見たり、漢文学の理解に欠かせない儒教や道教に関係する史跡を訪れています。

図書館学・現代文学ゼミ
図書館、文学館、街の本屋、古本屋、文学碑など、東京都内の本のある空間や文学史跡を訪れることで、それらがなぜ世の中で必要とされ、どのような理念で運営・設置され、どのようにして魅力的な空間をつくっているのかを実際に見て回ります。
Topic2文学散歩
文学作品ゆかりの地を訪ね歩く文学散歩。令和6年度は、「三島由紀夫と神島」と題して、伊勢湾に浮かぶ神島への文学散歩を実施。三島由紀夫が『潮騒』を書くにあたって逗留した寺田家でゆかりの品々を見たり、小説に登場する監的哨などをたどったりしつつ、神島を一周しました。学外へと足を伸ばす文学散歩は、文字からだけでは分からない作品の雰囲気を実体験できる貴重な機会となっています。

Topic2ビブリオバトル
ビブリオバトルとは、参加者が好きな本について紹介し、聞き手がその本を「どれだけ読みたくなったか」で競う、知の格闘技です。国文学科では授業にビブリオバトルを取り入れ、読解力と言葉による表現力の向上に役立てています。

皇學館大学ビブリオバトルサークル「ビブロフィリア」について
一冊の本を読み終わったときの感動を誰かと分かち合いたい。
みんなで集まって語り合える場所がほしい。
そんな想いから、ビブロフィリアは生まれました。
「ビブロフィリア」とは、本が好きな人、愛書家のことです。
読書が楽しみな人、本屋という空間が好きな人、
図書館が好きな人、将来は出版界で働きたい人、
本にかかわるあらゆることが好きな人たちが、
このサークルをつくっています。
今まで読んできた本、皇學館大学での学生生活、
これからの人生などについて、皆で語り合ってみませんか。
想いを、言葉に。皇學館大学 ビブロフィリア
活動について
ビブロフィリアでは、主にビブリオバトルを中心とした交流会や、
三重県内各地のビブリオバトル大会の支援活動などを行っています。
活動といっても、サークルに縛られるようなものにはしたくありません。
活動への、かかわり方は基本的に自由です。
大学のサークルですので、会員は皇學館大学の学生のみとなりますが、活動への参加・協力はどなたでも歓迎します。
年齢や身分に縛られず、誰もが自由に語り合える場所を、参加者全員がつくり上げていく。そんなサークルを目指しています。
平成24年7月24日に設立、主に皇學館大学附属図書館にて活動しています。
ビブロフィリアの理念
- 活動を通して各人の知性を培う
- 文化的活動のための場を提供する